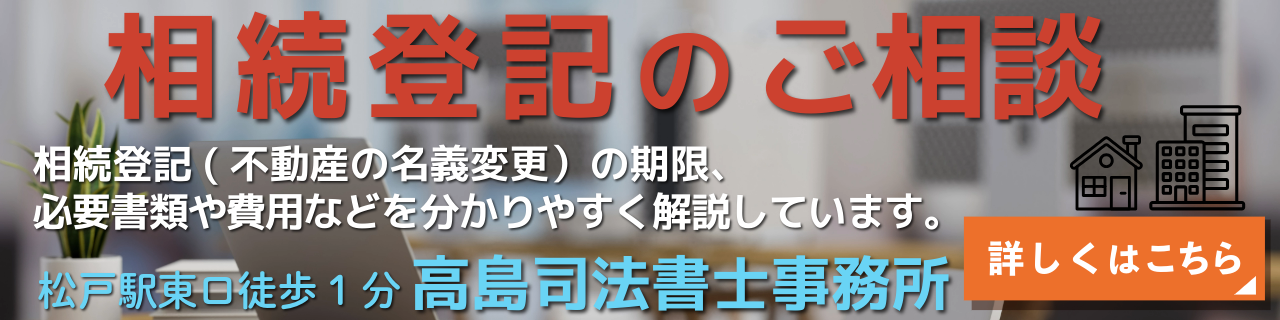相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務化)
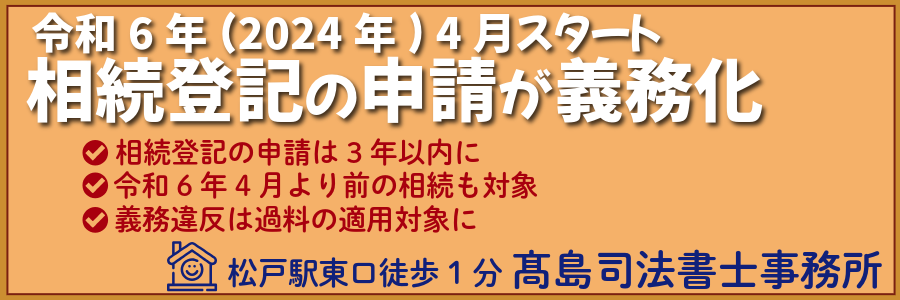
(最終更新日:2025年7月14日)
相続登記の申請が義務に
・2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(相続による不動産の名義変更)の申請が義務化されています。相続登記の申請の期限は、相続開始から3年以内となるのが原則です。
・相続登記の申請の義務化の対象となるのは、これから新たに相続する不動産だけでなく、令和6年4月1日よりも前に相続している不動産も対象となります。
・相続登記の申請義務に正当な理由なく違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。
不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務となっています。
改正前の不動産登記法では、相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をすることは義務ではありませんでした。相続登記をして自分の名義に変更したいと考える人だけが手続きをすればよかったというわけです。
それが、上記の法律改正により相続登記の申請は3年以内におこなうことが義務化されたということです。
また、相続登記の申請をすべき義務がある人が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
このページでは相続登記の義務化および申請期限のほか、相続登記義務化に関連して変更となることについて解説しています。不動産登記の専門家ではない一般の方がすべてを理解する必要はありません。相続登記を司法書士に依頼する場合、法律改正により必要となる手続きについては司法書士がご案内しますので、興味のある箇所だけご確認ください。
相続登記(相続による不動産の名義変更)の全般についての解説は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)による相続登記のページをご覧ください。また、当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務に)
2-1.3年の期限はいつスタートするのか
2-2.相続登記の申請の期限
2-3.相続登記の申請の期限
1.相続登記の義務化とは
相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されています。
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければなりません。
改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするかどうかは任意だったわけです。
実際には、相続があったときには、数年のうちに相続登記をおこなっている場合が多かったものの、相続登記をしないまま長い年月が経過している不動産も少なからず存在していました。それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されたわけです。
また、法定相続による相続登記がされた後に、遺産分割協議が成立したときには、その遺産分割によって相続分を超えて所有権を取得した人は、その遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記の申請をしなければなりません。
ただし、遺産分割協議の時から3年以内というのは、法定相続による相続登記をしている場合についてですので、遺産分割協議をしないでいれば3年の期限を先延ばしに出来るということではないので注意が必要です。
なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。
相続により所有権を取得した者は、遺産分割の日または令和6年4月1日(改正後不動産登記法第76条の2の施行日)のいずれか遅い日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされているわけです。
よって、現時点で相続登記がおこなわれていない不動産はその全てが義務化の対象となっていますから、できる限りすみやかに相続登記の申請がおこなえるよう準備を進めていく必要があります。
どうやって手続きを進めていけばわからない場合には、まず最初に司法書士へ相談することをおすすめします。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
2.相続登記の申請の期限
2-1.3年の期限はいつスタートするのか
相続登記の申請の期限がスタートするのは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知ったときです。このときから3年以内に相続登記の申請をしなければならないわけです。
そのため、「被相続人と疎遠だったため死亡の事実を知らなかった」とか、「被相続人が死亡したのは知っていたが不動産を所有していたのを知らなかった」というような場合には、それらの事実を知ったときから3年の期限がスタートすることになります。
しかしながら、上記のような特別な事情が存在しない、同居のご家族が所有していたご自宅(土地家屋、マンションなど)についての相続などの場合には、相続開始(不動産所有者が亡くなられた日)から3年以内が相続登記の申請期限になるのが通常です。
よって、被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が2名以上いる場合には、相続開始から3年以内に遺産分割協議をし、相続登記の申請をしなければならないのが原則であることとなります。
また、遺言により不動産を取得した場合についても、遺言により不動産を相続したのを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2-2.遺産分割協議をしていない場合の期限
今回の法律改正では、遺産分割協議が成立した場合についての相続登記の申請期限についても定められています(不動産登記法第76条の2第2項)。しかし、これは遺産分割協議が成立する前に、法定相続による相続登記をしていたときについての規定です(相続人申告登記をしていた場合についても同様の規定があります。詳しくは後述します。)。
そのため、ただ単に相続人の間で遺産分割についての協議をしていないというような場合には、相続登記の申請義務は相続開始時から3年以内であるのが原則です。よって、遺産分割協議をしないでいれば3年の期限を先延ばしに出来るというものではないので注意が必要です。
ただし、相続登記をしないことに正当な理由がある場合には、過料の適用対象外となります。この正当な理由として、「相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合」があるので、正当な理由により遺産分割協議が成立しない場合には3年が経過しても過料の適用対象にならないこともあり得ます。
それでも、「相続人が極めて多数に上り・・・」というようなケースは、相続が開始してから長い年月が経過し、何代にもわたって数次相続が開始しているような場合を指しているとのであり、今後新たに開始する相続がこれに該当することは通常ありません。
よって、遺産分割協議が出来ないでいるうちに3年が経過してしまうことで、相続登記の申請義務違反となるのを避けるためには、後で解説する相続人申告登記をしておく必要があることになります。
2-3.令和6年4月1日より前の相続も義務化の対象
相続登記申請の義務化は、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても対象となります。よって、現時点ですでに相続が開始しているものの、相続登記をしていない不動産についても、すべて相続登記の申請をする義務があることになります。
ただし、この場合の相続登記については3年間の猶予期間があります。この猶予期間は「令和6年4月1日から3年」、または「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年」となります。
よって、令和6年4月1日の時点で、まだ相続登記をしていないことを認識していた不動産がある場合については、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記の申請をする義務があることになります
今までは相続登記をするのが義務ではなかったため、所有権の登記名義人が亡くなってから何十年も経過しているが相続登記をしていないという不動産も数多く存在します。そのような場合、相続人であった方が更に亡くなられたことなどにより、相続人となる当事者が多くなり過ぎて手続きが困難になっているかもしれません。
そのような場合であっても、なんとか相続登記の手続きを進めていけるように努めていく必要があります。どのように手続きを進めていくべきか、また、費用がどのくらいかかるのかなど、まずは司法書士にご相談ください(千葉県松戸市の高島司法書士事務所へのご相談はこちらからどうぞ)。
3.相続人申告登記が新設されました
相続人申告登記とは、相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度です。
相続登記の申請をするためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの書類を収集し、法定相続人の全員による遺産分割協議を成立させる必要があります(遺産分割協議による相続登記の場合)。
これらの手続きを、相続登記申請の期限である3年以内に済ませることが難しい場合などに、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにするために新設されたのが、相続人申告登記の制度です。
相続人申告登記は、相続登記と比べて必要な戸籍等が少なく手続きも簡単であり、また、他の相続人の協力が得られない場合であっても、相続人中の1人のみが申出人となって手続きをすることも可能です。
ただし、相続人申告登記により相続登記の申請義務を履行している場合であっても、その相続した不動産を売却したり、ローン借入にともなう抵当権設定などをするためには、事前に相続登記をしなければなりません。
また、相続人申告登記をしている場合であっても、その後に、相続人による遺産分割協議が成立した場合には、その遺産分割の日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければなりません。
したがって、相続人申告登記は、相続登記の申請義務違反になることを避けるためにおこなうものであり、相続人申告登記をすれば相続登記はしないでよいというものではありません。
相続人申告登記の手続きや相続人申出書の作成について詳しくは、「相続人申告登記」のページをご覧ください
4.相続登記をしない「正当な理由」について
相続登記の申請をすべき義務がある相続人が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処するとされていますが、この正当な理由について、法務省による「相続登記の申請義務化に関するQ&A」のページで次のように書かれています。
相続登記の義務の履行期間内において、次の(1)から(5)までのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められます。
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
5.所有権登記名義人住所(氏名)等の変更登記申請の義務化
所有権登記名義人の氏名や住所についての変更があったときの、所有権登記名義人氏名(住所)等の変更登記申請も義務化されることとなります(改正不動産登記法76条の5、施行日は令和8年4月1日)。
不動産の登記簿(登記情報)には、不動産所有している人の住所と氏名(法人の場合は(法人の場合は本店と商号)が記載されています。引っ越しや結婚(離婚)などにより住所や氏名が変わっても、この登記されている住所や氏名)が自動的に変更されるわけではなく、登記名義人住所(または氏名)変更の登記を申請する必要があります。
これまでは、登記名義人住所(または氏名)変更の登記を申請するのは義務でなかったため、ずっと前に引っ越しをしたが登記されている住所は昔のままというケースも多くありました。それが、相続登記が義務化されるにともなって、登記名義人住所(または氏名)変更の登記申請も義務化されることとなったのです。
なお、この改正法の施行は2026年(令和8年)4月1日ですが、それ以前に住所氏名などが変更になっている場合も所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記申請義務化の対象となります。
改正後不動産登記法第76条の5(令和8年4月1日施行)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
6.検索用情報の申出(職権による住所等変更登記)
令和8年4月1日から、所有権登記名義人氏名(住所)等の変更登記申請も義務化されるのとともに、この登記申請義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が職権により所有権登記名義人変更などの登記をすることができるようになります。
この職権による住所等変更登記の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
検索用情報の申出をする必要があるのは、所有権保存登記、所有権移転の登記などです。ただし、所有権の登記名義人となるのが、法人である場合、海外居住者である場合などは、検索用情報の申出をすることはできません。
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
なお、登記名義人となる人のメールアドレスがない場合には、「メールアドレスなし」とすることもできます。この場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。
検索用情報の申出の方法、申出書の記載例等について詳しくは、「検索用情報の申出」のページをご覧ください。
7.参照条文等(相続登記の義務化関連)
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
改正後不動産登記法第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
(相続人である旨の申出等)
第76条の3 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(所有権の登記名義人についての符号の表示)
第76条の4 登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
(職権による氏名等の変更の登記)
第76条の6 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
第164条(過料)
第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
2 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ